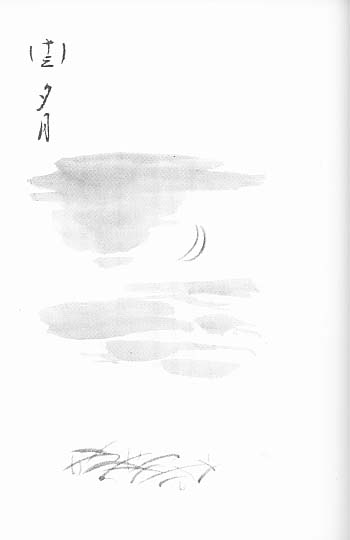
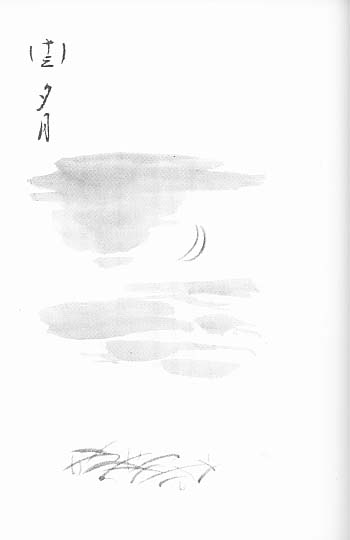
十三、夕月
登勢が部屋へ入って行くと柳沢夫人が、
「坊やが高い熱がしてるの、二三日食事が進まないと思いながら気に留めなかったら、熱が四十度もあるの、朝は八度程だったのに。」
と言った。
坊やはぐったりとして、色白の顔が熱の為に赫らんで、眼は充血していた。風邪がこじれた様子だ。留里と同年であるが、女の子と違って男の子は口が重く、言葉が少ないので、一層病気が判らなかったらしい。栄養不足から、誰も彼もが体力も病気への抵抗力も減退しているのであろう。まして幼児には栄養が必要なのだ。〃栄養失調〃それは何と悲しい言葉だろうか!。
登勢は何とも手のほどこしようもないあせりに襲われた。
手持ちの薬品を探したが、目ぼしい物は何も無かった。アスピリンの錠剤と健胃錠しか無かった。注射液もオバホルモンが三本銭っているだけだった。アクチゾール2・の注射液も使い果して無くなっていた。こんな時に独逸バイエルの会社のオムナジン2・注射液があれぱどんなに、心強いか!。代用品の国産オムヤノンの注射液でも---。心が焦ってもどうしようもなかった。アスピリンの錠剤六分の一錠程をつぶして柳沢夫人の持っていたクレオソート丸を一粒飲ませた。けれども効験は余りなく、熱は四十度近くを少し上下するばかりで夜になった。その夜坊やは熱におびえ、何度も泣声をあげて眠りから醒めた。暁近くなって、少し眠り始めたので、皆もそっと寝に就いた。
やがて底冷える朝霧と共に朝が静かに訪れた。どんよりと暗い運命の日の訪れであった。朝になっても柳沢の坊やの熱は三十九度八分を下らなかった。柳沢夫人は再びクレオソート丸とアスピリン錠のつぶしたのを少量飲ませた。お昼前になって熱は少しずつ下り始めた。熱を計ると八度五分になっていた。
夜通し坊やの看護をして疲れている柳沢夫人と代って、樗木が坊やを看る事になった。
熱が八度代に下っても食欲はなく、坊やはおも湯を少しだけ飲んだ。樗木がお茶を静かに持って行くと、咽喉が乾くのかお茶をよく飲んだ。そして又眠りにおちた。
二、三時間が過ぎた。樗木は静かに坊やを看ていた。咳が二つ三つ続けて出て坊やはうっすらと眼を開いた。赫らんでいた顔がさめて青白く冴えた可愛いい坊やの額に手を当てると、不思議に熱は引いていた。
思わず樗木は叫んだ。
「奥さん!。熱が下りましたよ。」
「良かったね!!。」
幸子も栄子も面を輝かせて喜んだ。熱を計ると六度五分になっていた。柳沢夫人も登勢もほっとした。誰の胸にもほのぼのとした安堵の思いが流れた。
けれど坊やは青白い顔に黒く澄んだ瞳を力なく見開いたまま、疲れ切って泣く事も笑う事もしなかった。熱が下ったというのに食欲がなく、お粥も食べなかった。
樗木がお茶を持って行っても、もう坊やはお茶を飲もうとしなかった。けれど素人の悲しさ、熱が下り、虚脱の状態が起きて幼い生命に危機が迫っているのを誰も感知出来なかった。よしんば感知出来たとしても何が出来たであろうか?。内服薬もなく注射薬もなく、医師も居ないのだ。皆が坊やの快復を信じていた。
午後三時頃だった。登勢は赤ん坊(舅の秀之助の秀を貰って秀坊と呼んだ。)にお乳を飲ませていた。
「沢山、沢山、お飲み。」
余りお乳を飲まない秀坊に、少しでも多くお乳を飲ます為に頬をつついている時、急に柳沢の坊やがクシャミをした。
「クシャン。クシャン。」と二度続いて出た拍子に鼻が「クシュン!」と出た。
「あっ!大変だ!。」
樗木が大きな声を出した。
皆が駈け寄ったがそれが最後であった。蒼白となった額面。口唇はチアノーゼを起し、両鼻孔から鼻汁を出して….-。
本当に一瞬の出来事であった。快方に向ったとのみ考えていた人々は、唖然としてなすすべを知らず、唯夢中で坊やの名を呼んだがー。
呼び声は空しい叫びに終った。
やがて二才の幼い坊やが黄泉へ独りで旅立つ別離の悲しみが皆を支配した。再びあの可愛い「アーチャン。」と云う声を聞く事は出来ないのだ。柳沢夫人の身も世もない慟哭!!。
幸子や栄子の口から洩れる鳴咽!。登勢達のすすり泣き!。そして樗木の男泣き!。汚れを知らぬ幼い坊やの魂は人々の涙に送られて静かに昇天して行った。
その夜はぼろ官舎の登勢達の部屋で橋口夫人、柳沢夫人、樗木、舟元、登勢の五人がお通夜をした。その翌日の夕方、柳沢の坊やの亡骸(なきがら)は、りんごの空箱に入れて茶毘(たび)に付される事となった。
その日、樗木はまるで自分の息子の様に可愛がっていた柳沢の坊やを、火葬にするのが辛くて、独りで出かける勇気がなかなか出なかった。
そこで、ソ連軍の仕事から帰るとすぐ、隣り官舎へ行って見た。
元部隊長官舎付の古角元上等兵が気軽に、
「一緒に行きまほか?。」と腰をあげてついて来てくれた。官舎の裏山から枯木を沢山採って来て、若い古角上等兵が一緒に来て呉れるのにいくらか元気づけられて、樗木は坊やの死体の入ったりんご箱を肩に担いでぼろ官舎を南へ下りて行った。
以前のかい楷行社へ通じる赤土の原っばを火葬場に選んだ。
枯木には樗木が火を点じた。異郷の地で我が子の様にいつくしんだ幼い者の骸(むくろ)を荒野ケ原で焼かねばならぬ敗戦国民の哀れさが、樗木から言葉を奪った様に、彼は黙然として焚火を見つめていた。やがてパチパチと枯木のはぜる音と共に髪のこげる臭いとも、脂の焼ける臭いとも判らぬ胸元につかえる厭な臭いが、辺りに漂い始めた。
そのうち火力のついた枯木は、焔を上げて炎々と燃え盛って来た。突然!。パン!!と大きな音と共に死体から何かが飛び散って、樗木と古角の全身に異常な臭いが降りかかった。
残雪が元階行社の荒れた建物の北側に白く見えるのが樗木の心を一層佗びしくした。僅かの遺骨を拾って、ぼろ官舎に帰った樗木は全で言葉を失なった人の様に、
「御苦労様でした。」という柳沢夫人に無言のまま坊やの遺骨を手渡して風呂場へ入った。
いくら洗っても洗っても、柳沢坊やの屍臭が消え失せぬばかりか、凝固した悲しみが胸の奥深く突き上って来る様で樗木は何杯となく水をかぶった。
柳沢夫人の嘆きは傍目にも哀れな程であった。明るい性格の夫人の顔から一切の笑いが消え去って、その面は愁嘆に沈んでいった。
夫人は半月後に死んだ坊やの生れ代りの様な男の児を出産したが、この赤ん坊の誕生にも慰められる事は無く、死んだ坊やの事が彼女の脳裏から離れないのだった。「上州名物、嬶天下に空っ風!一」と云う彼女の威勢のいい言葉は以後聞く事は出来なくなった。
柳沢の坊やが死亡してから二、三日が過ぎた。
雪は跡形もなく消え去って、少しずつ春が近づく足音が、そっと聞こえて来る様な日和ではあったが、柳沢夫人の心は、雪に閉ざされた様に重く、登勢も他の夫人達も冬の中に居る様な心の寒さであった。
登勢は仕事を求めて二〇二号官舎へ行く方がいくらか心が救われた。二〇二号官舎へ行くと、珍らしくマイヨール(少佐)がいた。
マイヨールは、登勢がお産で休む以前に、(一月末に)二〇二号官舎のペチカの部屋に、引越して来ていた。登勢は最初、マイヨール(少佐)を見た途端に、夢野久作の小説、大正十年頃のハルビンのキタイスカヤ街を舞台に、展開された、日、露、満、三国の三つ巴の事件を書いた「氷の涯」に登場する人物オスロフを連想した。
黒い髪、碧い眼のスラブ系の六尺五、六寸の巨漢ロシヤ人のオスロフに、イメージかびったりと来たので、登勢は勝手にマイヨールをオスロフと名付けていた。
その日、登勢の後から二人の日本女性が官舎へ来た。
「何か仕事はないでしょうか?」オスロフは二人を、
「こちらへ入って来なさい。」と招じ入れて話を始めた。
「名前は?」
「稚内」
「飯田」
マイヨールは稚内夫人を指して云った。
今晩七時に仕事に来なさい。」
「二人では?」
「独りで。」
稚内、飯田の両夫人に聞かれて、登勢はオスロフの話を説明した。マダムクチャカアの姿が見えないので登勢は早く帰る事にして、二人の夫人の後から、ぼろ官舎へ帰った。
登勢が翌日、二〇二号官舎へ行くと、黒い胸毛の胸をはだけ、オスロフは不機嫌な顔をしていた。稚内夫人が前夜来なかったのは、登勢が邪魔をした様に思ったのか、留里と敏夫に、
「退け」.と云わぬばかりにして、荒々しく、官舎を出て行った。ドアが閉まると、マルキンが肩をすくめた。登勢は子供をうるさそうにするオスロフが厭であった。敏夫を可愛がるジンジャーともオスロフは合わない様子であった。
(雲に彗ゆる高千穂の、高嶺おろしに草も木も、なびき伏しけん……)と云う毎年、登勢達の歌い馴れ、聞きなれた歌も聞く事もなく、紀元節には引揚が開始されると云う話も実現せずに、二月十一日はとっくに過ぎてしまっていた。
登勢達の頭上で、シャンデリヤの様に輝いていた紀元節帰還説は、何時の間にか消えてしまって、日本人会とソ連側との引揚交渉は、難航したまま何処かで坐礁していた。
ソ連の「第四次五ケ年計画」が発表され、炭坑へ使役に行った人々が「五ケ年計画の石炭増産」を奨励されて、ぼろ官舎へ帰って来たのは、二月も段々終りに近づいた風の強い日だった。雪がまだ残っている秋乙の凍てついた地面が冷気を発散していた。しかし昨年の冬より気温の暖いのが、登勢達ぼろ官舎の住民にとっては大きな救いであった。
その頃在北鮮の日本人の中で一番困窮のどん底にあったのは、ソ連軍の参戦によって、満洲から避難して来た人達であっただろう。
「満洲避難民の方達」と云って登勢達は、同情していたが、援助する力もなく、日本人会を通じて、ぼろ官舎からも坂元夫人が代表で、衣類やお金を持って時々、慰問に行くのが関の山であった。お正月前に坂本夫人が行った時には、各自に丸で顔の写りそうな程薄いお粥を造ってすすっていたと云う話であった。登勢達もいずれ近い将来にそんな日が来ると云う生活の不安は消えなかった。でも現在のところ、ぼろ官舎の住民だけの共同炊飯で毎朝一日分の配給が行われていた。しかし何時迄御飯が食べられるかは疑問であった。それにしてもお米を一叺も呉れたジンジャーに、そしてマダムにも、何かお礼をしたいと登勢は思った。彼女はガーゼニ校に縁飾りを編んでハンカチーフを作った。それに二枚ずつShinsiya
、 Kuchiyaka と名前を入れて、二〇二号官舎へと持って行った。
二、三日休んでいる間にカピタンジンジャーが遠くへ左遷された事など登勢は露知らなかった。
マダムクチャカアは登勢の差し出したハンカチを受け取るとローマ字の筆記体で書かれた名前をロシヤ語として読んだ。「キメイエカ?。」登勢が「クチャカアー。」と読み直すと、「スパシーバ!!〃(有難う)。」と云って微笑した。
残りの2枚を、
「これはジンジャーカピタンに。」と云うとマダムクチャカァとマルキンは当惑げに顔を見合せて、
「フチラーショールオムスク、(昨日オムスクヘ行った。」と言葉少なに答えた。
「えっ?。」と云ったま、、言葉はなく登勢は考えた。秘密主義の共産圏〃ジンジャーは登勢親子に対して親切でありすぎた。
乾パン一箱(60袋)、米一叺を気前よく呉れた。そして登勢の別誂の色紋付(登勢の母が図案を考案して作ったもので、リンズ生地の地紋のバラを生かし渋いうぐいす色の地に薔薇の花を手描き染にして裾模様の上前には刺繍を入れたゴージャスな衣裳)も高く買取って呉れた。
日本人捕虜の家族に親切にした事を密告されて遠くへ飛ばされたのではないかしら?。少しの自由すらなく平等の枠からはみ出した者を互に互をスパイして、密告する事により、点数を稼ぐシステム。実に不愉快この上ない事と思ったが、子が親を、親が子を、友が親友を、夫が妻を、妻が夫を裏切って密告するという悲しい不信があちこちで繰返されているのだ。シンシャーとの別離は登勢達親子が原因ではないだろうか?という痛みを登勢の胸に残した。登勢は悪いとは思いながら、オスロフが密告したのではないかと云う疑いを持たすには居られなかった。
その夜、登勢は夢を見た。幼い頃に見た、おどりの夕月の舞台だったのか、絵本のさし絵なのか判然としないが、夕月の下を月光を背に誰ともわからない淋しげな人影が、遥かな広野へと歩いていた。それは気の毒にも左遷されたジンジャーだったのかも知れない。
柳沢の坊やの死は、栄養失調が病気にどれ程無抵抗であるかを登勢に思い知らせた。
栄養失調の恐ろしさを知った登勢は、子供の生命を病気から守る為にリンゴや卵をよく買った。それ以外にも荷車を引いて売りに来る菜園の中国人(元二五〇部隊へ野菜を販売納入していた)から人参(VABCとして)や、牛蒡(VL、催乳剤)を買って、人参は皮は味噌汁の実に、後はおろして生食していた。味噌は粉味噌、米は古米(一昨年)なので、気をつけているつもりでも、ぼろ官舎の人々の栄養不足は段々とつのって、顔がむくみ、入浴の度に段々と痩せて行くのが自分でわかるのだった。そこで登勢は一計を案じた。
寺洞へ買い物に行く男の人にたのんで、煮干し、干えび、糠を買って来て貰った。煮干し、干えびと共に糠を煮て、朝晩二回の食事には鶏か馬の様に糠を沢山親子で食べた。留里と敏夫をつれて二〇二号官舎へ通っては、二〇二号官舎で子供にだけ茄卵を作って軽く食べさせる事で、幼児の四回食には及ばぬ迄も少しでも補えればと思っていた。播州の塩の名産地に育った登勢は、これまで塩がそんなに貴重品とは思っていなかった。人体に必要な事は理解していても、以前は三盆白と見分けがつかない程真白な食卓塩がサラサラとこぼれても掃き捨ててしまっていた。それが今、北鮮では大切な大切な必需品として貴重品となった。甲斐の旧敵(武田信玄)に塩を送った上杉謙信の美談が今、切実なものとして登勢に感じられるのだった。
灰色の岩塩の一片を茄玉子に添えながら、又しても何時播州へ帰れるのだろうか?と思った。登勢には播州の塩迄が懐かしく恋しかった。
三月に入って間もない日だった。
登勢が二〇二号官舎へ行くとパーシャ曹長の友人セルゲイが来ていた。彼等はテーブルの上にグラビヤの画報を置いて楽しそうに話をしていた。
パーシャ曹長は、
「岡田奥さん!」と登勢を呼んで、「ショーロフを知っているか?」と聞いた。
登勢が「ヤ、ニスナイユ(知らない)」と答えるとさも残念そうに、
「ショーロフ、ショーロフ」と繰返して、ショーロフの小説『静かなドン(河)』の意味なのか?、彼(セルゲイ)は有名なドン、コサックだと云った。セルゲイは登勢を真直ぐに見て
「ウミニヤツリツサティ(私は30才)、ディスコールカ(君は何本)?」と聞いた。登勢はとっさに嘘を云った。
「サウラックフタローイ(42才)」傍からパーシャ曹長が云った。
「嘘だ。マダムは20才だ。」(小柄な日本人ののっぺりした丸顔は外人と比べるとどうしても稚なく若く見えるらしかった)パーシャは上機嫌だった。
「近日セルゲイはモスコーへ帰る。彼は奥さんが死んで居ないのだ。」と云った。
セルゲイは登勢に、一緒にモスコーへ行こう。」と言った。
登勢が驚いて、
「私には夫が居ます(ヤ、ムッシーナイエステー。)」と云うと、
「君の夫は三合里から遠くへ行ってしまってもう帰って来ない。」と云った。
「いいえ、冗談は止めましょう。私には子供も沢山居ます。」
「大丈夫、子供は国が育てて呉れる。結婚してモスコーへ行こう。」
「ニエト、ニエト(駄目駄目)」と云いながら登勢は単純なソ連兵を相手にこんな話をするのは馬鹿らしかった。と云うよりも情なくみじめであった。生活の為に日本婦人が、ソ連のマイヨール(佐官)の2号になった話や、スピーチマダム(売春婦)になった人の事も聞いていた。セルゲイはパーシャを見て肩をすくめた。パーシャは登勢を見ながら
「ニエト、ニエト(駄目駄目)と真似をした。登勢もむきになって怒る事もないと思いなおして始めて笑った。パーシャは少し飲んだウオッカのせいもあって餅舌であった。マルクスの資本論、唯物論から話はボルシェヴィキに及んだ。彼等はプルードンやヘーゲル、そしてエンゲルスと気炎をあげた。そして
「マルクスは失敗してもレーニンは成功した。レーニンはえらい。ハラショーだ。」と話が一段落してセルゲイは帰って行った。
そのうち「おんどる」の部屋からクチャカァも出て来て話に加わった。と云うよりにこにこしてグラビヤを眺め聞き役であった。テーブルの上のグラビヤには、二月廿日付で南サハリン、千島列島と大連(ターリェン)、旅順(リュイシュン)の地図が出ていた。
一九〇五年と大きな数字の下に水師営の乃木将軍とステッセル将軍の写真に「のぎまれすけ」と云ってから、地図の下の大きな文字で一九四五年と書かれたのを示して、四十年振りに樺太を取り返したという顔でパーシャは笑った。
北方領土問題、漁業問題として30年後迄も、鈴木、イシコフ会談等と日本にとって重要な意味をもつ事柄が、その時期に定まった委しい事情など少しも知らず、登勢は漠然とグラビヤを眺めていた。グラビヤの次の頁には、ロシヤ人の女性の写真が出ていた。この女性は子供を沢山(10人以上)生んで育てた人で婦人の日に表彰され、国から勲章と年金があたるのだとパーシャは説明した。三月八日は婦人の日で、女性にミモザの花を贈り、贈物をするのだと云った。そしてその日は、「マルキンと私」が炊事も洗濯も掃除もしてクチャヵアマダムは休養する日だと云った。マダムが一日だけね-」と笑うと登勢に
「日本には女性が休養して男性が家事や雑用をする日は無いでしょう。」とパーシャは自慢をした。
大陸の冬は長く冷えきった万物は、春を迎えるのも手間どっていた。
三月になっても凍てついた秋乙の地面は冬との名残りがつきず、樹々の芽は春の訪れを静かに待っていた。
二〇二号官舎でも樹々の中でめぼしいものは切り倒されて、おんどるの焚きつけや、ペチカの焚きつけになって消えてしまっていた。美しい花をつける小梅の樹すらその影もない。
二〇二号官舎へ入って行くと誰も居なくて、マルキンが独り居た。何かいやに愛想がよく、パンと黒砂糖を出して来て、敏夫と留里にすすめた。マルキンは今日こそと登勢の来るのを手ぐすねひいていたのだった。パンと黒砂糖は番犬の餌だった。
登勢はオスロフの部屋へ掃除に入って行くマルキンの後からペチカのよく利いた部屋へ入って行った。登勢はオスロフの私室に入った事は始めてであった。(登勢が掃除するペチカの焚口はテーブルのある皆の集まる部屋であったから)
オスロフの部屋は右手に大きなWベット。左手の南向の窓側に机と椅子がペチカの背と並ぶ位置に置いてあった。掃除にかかろうとベットのシーツに手を延ばした時だった。上背のあるマルキンの体がいきなり登勢に覆い被さって来た。余りにも急な出来事であった。登勢は驚いた。羽交締めにされた体を振りほどこうともがいたが、マルキンは磐石の如くのしかかって来た。もはや絶体絶命!「助けて!。トシチャン!」何を叫んでいるのか彼女は自分でも判らず夢中で叫んだ。その声に一瞬マルキンはひるんだ。すかさず登勢は渾身の力をこめて、マルキンを振りほどこうともがいた。自由を取り戻した登勢の左手が(登勢は左利き)がむしゃらにマルキンに向って飛んだ。操み合いながら出口へ走った登勢は襖を開こうとした。襖には何時の間にか鍵がかけられていた。彼女は、「トシチャン。トシチャン!。」と叫びながら襖を叩いてこわしても良いと思った。敏夫と留男も母親のただならぬ声に馳せつけて来て、襖を外から叩き始めた。留里は半泣きで、
「カーシャン!」「カーシャン!」と叫んだ。
事態かこヽに至ってはマルキンも鍵を外して襖を開けた。
襖の外には、五才の幼いナイトが黒砂糖の粉を口の周囲に一杯つけて立っていた。
「さあ、帰りましょう。」
帰り支度もそこそこに親子は二〇二号官舎を出た。
登勢は最初からソ連兵には充分警戒していたつもりだったのに、事なきを得たとは云うものの、マルキンに気をゆるして油断していた自分に腹を立てていた。もうマダムの居ない時にはソ連兵のいる官舎へは絶対行くまいと警戒を新にした。
それから間もなくマルキンも何処がへ転勤して行った。ペトローと云う底ぬけに人の良い小柄な少年兵が代りに来た
パーシャ曹長の話によると、自称26才のマルキンは18才の鼻たれ小僧で、鼻の下に二本ローソクを立てていると云うのだった。登勢には別離を前にして背のびをして行動していたのだった。マルキンは子供だとパーシャはマダムクチャカアと顔を見合せて笑った。
三月になった頃から子供達の間に病気(三日麻疹、水泡瘡)が流行していた。
ぼろ官舎でも次々と感染してその日、敏夫は熱がしていた。五日程前に留里が水泡瘡にかかりやっと治癒したばかりであった。坂元の清が最初に罹り、橋口の浩や了とぼろ官舎の子供達の殆んどは何かの役の様に水泡瘡に罹った。最初の間に罹った児は、高熱と云う程の熱もなく水泡が出て治ったのに、段々後に罹る程病原菌が強くなっているのか?病気は重かった。
少し早い目の夕食を食べている時だった。敏夫が大きくガクガクと歯を鳴らしてお粥の様な柔かさの御飯を噛むのに気づいて、登勢が、「変な食べ方をしなさんな!」とたしなめた途端!。敏夫は急にお箸を持ったま、右手を上に差し上げて後へ倒れた。
「トシチャン」と云いながら額に手を当てるとすごく熱かった。(大変な熱だ)
登勢は「はっ!」と棒立になったまま呆然として咄嵯に脳の回転が止まった様な衝撃を受けた。(落ちつけ!。落ちついて!。舌を噛まぬように注意して静かに寝かせるのだ。出来れば暗くして浣腸をする)それは神の啓示であったのだろうか?。
彼女は亡き舅の声を聞いたと思った。亡き舅の声が彼女を力づけた。柳沢夫人と樗木が手伝って敏夫を寝かせた。
登勢は留里を背負うと浣腸薬を求めて、赤土の上に処々残雪を置いた戸外へ夢中で駈け出した。排便の後も昏々と眠り続けた敏夫が、けろりとして目を醒ましたのは夜の八時頃だった。
水泡瘡の流行はソ連側との間にも物議をかもした。
ソ連側は、日本人は沢山天然痘にかかったから、秋乙の日本人全部消毒風呂に入れて、その間に衣類を消毒し秋乙から一歩も外へ出さない。」と云い出した。日本側は、
「これは水泡瘡と云って絶対に天然痘ではない。」と云い張ったが、ソ連側は軍医迄が天然痘を主張してゆずらなかった。日本の軍医とソ連の医学の権医者が立ち合った結果天然痘ではないとの結論が出た。ソ連側は、
「ソ連は戦争では日本に無条件降伏をさせたが日本の医学には無条件降伏をする。」という言葉を吐いて談議はけりがついた。
昔から登勢達の地方では、三月上旬の奈良のお水取りが始まる頃は、毎年寒さが戻り、冷え込みがきついと云い古されていた。北鮮でもやはりその例に洩れず寒い日が続いていた。その頃〃四月にはソ連兵やその家族達が沢山秋乙の官舎へ転入して来る”という噂が流れて来た。
朝から春一番が吹き荒れて、空っ風が黄塵を突き飛ばす様に吹いていた。ソ連側と引揚交渉中の日本人会から橋元省三世話人(元二百五拾部隊家族達の代表)に突然に通達が来たのは、そんな日の午後だった。
三日後に全員秋乙を出発せよ。」との伝達は、皆の心に希望を持たせた。行く先は鎮南浦?。船で帰国だ?。桜の花咲く日本へ帰れる。故郷の荒神坂の桜並木や揖保川の岸辺のぼんぼりの灯が登勢の険に浮んだ。
明朝九時に愈々秋乙を出発すると云う前日の夕方だった。クチャカアマダムの使いで当番兵のペトロが登勢を訪ねて来た。
ペトロはしわくちゃの5円や10円の軍票を混ぜ合せた100円を、クチャカアマダムから預かって来たと云って手渡した。しわくちゃの軍票は掌の上で、人種は違っても人間の、心の暖かさを通わせていた。
「スパシーバー(有難う)。」
「お元気で。」
「ダスビダニヤ(さようなら)。」
〃もうこれでジンジャーやマルキンは云う迄もない事ながら、マダムクチャカアにもパーシャにもペトロにも、生涯再び会う事はあるまい。
別離の哀愁が登勢の胸に迫った。
ふと見上げた早春の空にうっすらとした夕月が懸って、戸外の肌寒さの中に佇む彼女を夕暮が静かに包んでいった。
ぼろ官舎の中では、明日の出発をひかえて活気に満ちた夫人達の声がしていた。
秋乙編 完