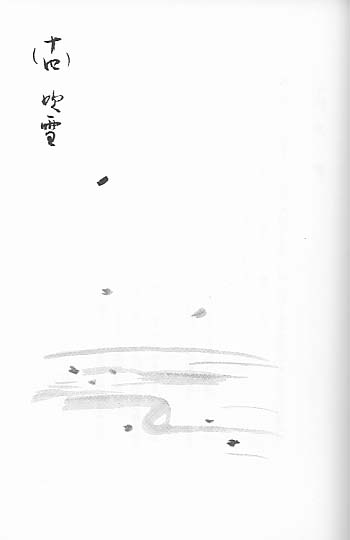
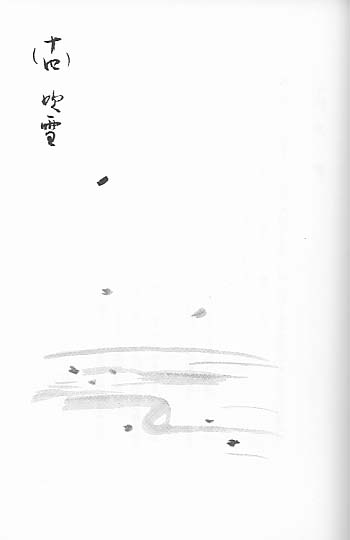
十四、吹雪
愈々秋乙を出発する日、夜明け前から酷しい冷え込み方で窓ガラスの外には霜がびっしりとついて、屋内の壁際のふとんの裾もしとど濡れていた。
「奥さん!一そんなに睡っていたら放っておくよ。」
樗木のそんな声で登勢は眼を醒ました。
まだ薄暗いのに思ったのはお天気のせいであった。もう時間は七時前らしかった。殆どの人が手荷物を手縫いのリユツクに詰めていた。行先は〃鎮南浦〃らしいという事である。
毛布は出来るだけ持って行く様と云う專、皆せっせと荷作りをしている。何処へ行くのか?。すぐ日本へ帰れるのか?。誰にも確実な事は判っていない。行先は鎮南浦としても乗船する迄は、いや、日本内地の土を踏む迄は決し安心出来ないのだ。
登勢は小さな赤ちやん用のふとんと調度品の中でも親子四人の生活必需品を布団袋に詰め込んだ。ぎりぎりの域を出ないのに結構大きな包となった。
どんな事態が何時生じても三人の子供(幼児)を守って内地へ還らねばならない悲壮な決意が登勢を支配していた。
荷物は舟元、小吉の若い男達の手でせっせとトラック迄はこばれた。
登勢は赤ん坊(秀坊)を四つ折にした毛布でくるみ、その上からおんぶ紐をかけて背おい、ねんねこを羽織った。
敏夫と留里にオーバを着せ、官舎の南の広い(約20m程)道路へ出た。もう道路にはソ連兵が運転するトラックが来ていた。トラックには一杯に荷物が積み込まれ縄がかけられていた。荷台に立ったままより、女・子供は荷物の上に座る方が楽であろうと云う事で、登勢等は山盛りの荷物の上に座った。登勢達が乗って、続いて一番最後に樗木がトラックに乗るや否や、もう車は発車した。登勢は留里が転げ落ちない様にと留里を抱え込んで、片手で荷物の掛け綱をつかんだ。登勢は敏夫が危なつかしく、敏夫のオーバを肘でおさえる様にして座った。けれど、どうしても敏夫を支える余裕がなかった。「敏ちゃん、縄をしっかりつかむのよ。」と声を掛けるのが精一杯であった。うっかり重心を失えば疾走するトラックから何時振り落とされるかも知れないのだ。広いだけが取り得の様な凸凹の道路を、若いソ連兵は乱暴な運転で迅って行く!
雪を誘う疾風が黄塵を舞わせながら頬に痛い程の冷たさを吹きつけて過ぎる!。登勢は、〃トラックから敏夫が若し振り落されたら大変だ〃と云う心配で唯敏夫をじっと見つめていた。
何処をどう走っているのかも何も判らず、冷たい油汗を額に惨ませて疾風に耐えている時間は随分と長く思われた。
本当は30分そこそこであっただろうか?。
やっと平壌駅で列車に乗り込んだ。列車は朝早くから動いていたらしく、登勢達は二番目の折返しの列車らしかった。殆んどが秋乙から来た人達である。全員が「内地へ還れる!。」と云う思いに喜びを面に漂よわせている。皆いそいそとして列車の席に腰をおろした。
緊張から解かれた様に柳沢の栄子が「あー、あー。」と大きな声を出したので皆がどっと笑った。〃鎮南浦で船に乗るのだ。これで内地へ還れる!〃云わず語らず皆の思いは帰国の船に乗っていた。
これから前途に幾山河が横たわり道を迷えば河は三途の川に続く事も、38度線の障害をも誰もが考える余裕を持って居なかった。
「ダモイ。東京(日本)!。(内地へ還る)」の夢を乗せて重い雪雲の下を汽車は「ゴトゴト」と走った。二時間半程も走った頃だった。
古角元上等兵(召集入隊以前は国鉄勤務の車掌であった。)が列車に廻って来た。彼は、「間もなく列車が止まります。この列車を消毒するそうですから皆さん下車して下さい。少し行った処にお風呂がありますから、お風呂に入ってから戻って来て再び汽車に乗って下さい。」
と明るいよく透る声で云った。
皆驚いてがやがや云いながらあわて下りる準備をした。その中に汽車が止まったのは小さな駅なのか?。駅舎らしい建物も無い田圃の真中であった。登勢は秀坊を再び四つ折の毛布で巻いておんぶした。少し以前より鉛色に重かった空からは、ちらちらと粉雪が落ち始めていた。
登勢はねんねこを羽織ったり敏夫と留里にオーバを着せたりするのに手間どって汽車を降りたのは最初の人から大分遅れていた。
そこから200メ−トル程先のお風呂場附近まで巾80・程のやっと2列で通れる畦道がついていた。柳沢夫人は〃これから日本へ引揚げて帰る迄お風呂に入れないかも知れない〃という危倶があった。この際入浴しておこうとばかり、大急ぎでお風呂場へと向った。彼女にも生後一ケ月余の男の赤ん坊がいるので幸子と栄子をせかせて手際よく風呂へ入った。
風呂場は山里の学校の分教場の様な建物であった。
入浴すると云っても日本の〃銭湯〃と全然違っていた。
脱衣した衣類は、くくって吊り下げ、一坪程の湯舟からくんだ手桶一杯だけの湯を裸体にかけて洗うのであった。
風呂へ入っている間に吊り下げた衣類は蒸気でむして乾燥消毒されているので風呂から出るとそれを着るしくみになっていた。
寒さの中で、湯舟の中に全身どんぶりっかつて暖まる日本の銭湯と違って、それはソ連式の入浴なのだ。建物は田圃の畦道から見えていたが、登勢は幼児3人を入浴させる事にとまどいを感じていたのでゆっくりと歩いた。次々と後から来た人が登勢達を押しのける様にして追い抜いていった。登勢が畦道の横に身をかわした様にしながらゆっくりゆっくりり100メ−トル程畦道を歩いた頃、もう入浴を終えた人達が帰ってくるのに出会った。二列で歩いた。登勢は一列になって入浴が終って帰っ来る人と入れ違いながら歩いた。
汽車降りた頃から、小雪は吹雪となって風呂上りの人々にも登勢達親子も気ぜわしく降りかかった。
「おお寒い!。」「冷えてしまう!。」「速く汽車に乗らないと……。」
足踏みをしながらすれ違いざま、「寒い」を連発して小足に駈けてゆく人達を見て登勢は愈々入浴しないで引きかえす決心をした。
20m程すれ違った頃、登勢の後に続く人が無くなった。
「今だ!!。」
登勢はくるりと敏夫と留里を後向きにさせると、靴を直す振りをしてしゃがんだ。そのまま、自分も後へ向きを変えると入浴の終った人達の列に混ぎれて歩き始めた。
再び皆が乗り込むと汽車は以前来た線路を少し戻ってから方向を変えてゆっくりと走り出した。
子供達はうとうととまどろみ始めていた。
線路の行き止まりで汽車を下ろされた人々は疲れていた。〃鎮南浦だ!〃愈々!〃〃内地帰還〃
誰もが期待と希望に疲れを忘れた。誰云うとなく「乗船の為埠頭へ行くのだ。」と云う言葉が流れた。
人々は重い足を力一杯軽やかに運んだが、少し行っては止まり、少しも進まない。近道だと云う道の両側に雑然とトタン屋根の建物がある材木置場らしい処を抜けやっと広い道に出た。
雪は止んでいたが登勢は、眼前に吹雪の舞う道が続く様な思いに囚われた。
前方に入口の前だけは鉄さくで周囲は有刺鉄線をめぐらせた埠頭の門が見えているのに行列はなかなか進まない。
「そんなにぐずぐずしていては今日中に船に乗れないねー。」
「門番が人数を数えているのだ……。」(ソ連兵は数をかぞえるのが不得手であった。)
皆で様々の憶測をしていると、「二百五拾部隊の家族は早く門前へ来て下さい。」
橋元省三世話役の声がした。
橋元が人数と名前を書いて来た帖面を渡し説明したので二百五拾部隊の家族達は優先的に埠頭の門をくぐった。
登勢達が連れて行かれた処は大きな米穀倉庫であった。綱で仕切がされ、男達の手で筵が運び込まれた。コンクリートの上に筵が敷かれ、どうにか休憩出来る場所が出来た。その後大分遅れて倉庫へ次々と人々が入って来て綱の仕切が増え、場所は段々と狭められて、一家族に一、五帖位の割になった。
綱の仕切りの処に、各自の荷物を積み上げて、小屋がけの芝居の桟敷の様な形になって、広さ20帖程が二百五拾部隊の家族全員の居場所となった。当分の間船を待って倉庫で暮らすと云う事であった。
今日中にでも乗船出来ると考えていた人々は、すっかり気落ちしてしまって、力無く筵の上にくず折れる様に腰を下した。
こうして登勢達の米穀倉庫での生活は始まった。
一週間程の間に、埠頭に建ち並んでいる米穀倉庫は、次々と送り込まれた日本人で全部一杯になった。班が構成され登勢達の二百五拾部隊は16班と呼ばれる様になった。
三月も終りに近づいていたが未だ寒さは厳しかった。
登勢達の住む倉庫と隣の倉庫との間は3米程も空いていたので、天気の良い日は日当りのよい空地は、人で一杯になった。その空地からは突堤が良く見えた。長く突き出た突堤に誰が植えたか桜の木が一本枝を張っていた。
四月になれば内地引揚げが開始されるだろう。〃桜咲く日本!〃。観念の世界に入り込んで、誰もが無口になっていた。桜!それは故国の花である。寒風に晒されながら、無言で桜の木を眺めるだけでも皆の心は柔らいだ。
埠頭は大同江の河口に位置していたので、突堤の向うにある海の広がりは、建物に邪魔されて見えなかった。けれども空を流れる雲や、入って来た船や、出て行く船は空地からよく見えた。見ていると、二隻船が入って来た。最初の間は、〃あの船に乗るのだろうか?。出発する日は?〃。と云う期待が多分にあった。しかしそれも空しく消えて行った。
帰国について何の音沙汰もなく周囲には監視のソ連兵が銃剣を着けて前哨に立っているのだ。
異国の地に、
〃捕虜として抑留されている〃現実がそこにあった。間もなく使役の割当が通達されて男達は毎日出て行く様になった。五彩を放って、大同江の河口に浮んでいた希望の風船は萎みきって、桜咲く美しい日本の夢も一緒にシャボン玉の様に消えてしまった。
倉庫は東西に長く、西に入口があった。(はっきりした方向は判らない)大きな扉の入口を入った処から奥(仮に東とする)へ一米程の巾に綱を引いて仕切り通路が作られていた。北側の中央にも扉があったが、中央の扉は水を運ぶ時とか燃料を運ぶとか食糧(お粥をはこぶ時以外は閉じられていた。
ドラム缶が北側の中央入口を入った処に置かれて、そこで皆の飲み水が沸かされていた。昼間はドラム缶で火が燃やされ始めたので、横に位置する16班は割合暖かい特等席になった。それでもコンクリートに一枚の藁筵を敷いて床代りにしただけの、だだっ広い倉庫は夜になるとよく冷えた。
倉庫の生活が始まって間もなく、鎮南浦へ移転途中の入浴がたたったのか、風邪や麻疹が流行して来た。一才未満の体力のない赤ん坊は風邪から肺炎を起し、熱も七度五分を越さないままでクシャミと共に鼻が出て呼吸が止まり、天国へと旅立って行った。
乳児や幼児を抱えた夫人達は夢中で一心不乱に看護をした。空地へ出る人も無く、倉庫の中は薄暗く、重苦しい空気に包まれていた。
登勢は麻疹が内攻して死ぬ幼児達を沢山目前にした。無気味な程に蒼白となった皮膚には、発疹の赤味などかけら程も無く、母親の嘆きをもその儘に幼い魂は昇天して行った。麻疹の流行に対して倉庫の日本人会の唯一人の医師の指示によって母親の免疫を我が児に与える方法が取られた。(現在の様に免疫抗体のガンマグロブリン等はなく麻疹に罹った児の発疹の出た日から五日目位が一番免疫性が強く少量五cc位で良いが、麻疹にかかってから、20年以上も経た免疫性では20ccを要すると云う)看護婦の経験と免許を持つ数人が早速動員され、母親の希望によって、その母親の腕から20ccの血液が採血され、クエン酸ナトリウムを混ぜて(血液の凝固を防ぐ為)幼児の臀筋に注射が打たれた。
その二、三日前から留里は37度5分程熱がしていた。麻疹の始めは風邪に似ている。麻疹は体力によってその症状に差は多いが、全身病である為、皮膚ばかりでなく、全身の粘膜すべてに発疹が出て、口内から胃壁に迄発疹が出てくる由、その為消化能力が落ちて、
下痢の症状を呈する事も多い由だった。登勢は自分の血液が留里の生命を守って呉れる様に神に念じながら20ccの血液注射で大きく赤く腫れ上った留里の臀部に温い湿布を当てて揉んでいた。
しかし次の日には却って熱が高く38度になって来た。その次の日も留里の熱は下らず、やはり38度を上下していた。そして五日目には三十八度五分にもなった。熱が高いのに発疹は表面に出ず、登勢は麻疹の内攻を恐れた。
麻疹が表面に出ると云う〃小林の烏犀角散〃が日本人会から希望者に斡旋されたのはそんな時であった。〃烏犀角散〃を飲ませた翌日、留里の顔にも手足、お腹にも発疹が現われて来た。これで峠を越すのかと思ったが、麻疹は咳を伴い、咽喉がぜいぜいと云う様になって、39度の高熱が続いた。配給の薄いお粥も食べず咽喉をこすのはお湯だけであった。
留里に気をとられていた登勢が、眼元が赤い様な敏夫の様子に気づいて検温すると38度もあった。翌日になると敏夫の熱は39度をこえ、額にもお腹にも地腫れがしたと思う程発疹が出て来た。ニケ持っている水筒に熱湯を入れ、湯たんぽの代用にして留里に使っていたのを一ケ敏夫に使わせたが、余りにも敏夫の熱が高いので、高熱に脳がおかされないかと登勢は、脳膜炎の事が心配になって、水枕で頭を冷した。そして肩が冷えない様に毛糸を二本どりで編んだ大人用の防寒シャツを着せてふとん代りとして寝かせた。
力無く眼を閉じている留里と違って、敏夫は動き廻るので、仕方なく敏夫にカルモチン半錠をのませた。やっと静かに水枕をして、熱っぽい顔をあどけなく上向けて敏夫は昏々と眠った。
鎮南浦の生活が始まってから街へ仕事に行く人も、持物を街へ売りに行く人も出来て来た。届けを出せば門番も最初程にやかましく云わなくなっていた。日本人会にたのめば、持物は売りに出して貰えたが、代金の受取りが大分遅れた。それで多くの人は、倉庫から街へ出かけて行く元軍属の中井にたのんで、様々の物を売って貰っていた。登勢も鰐皮のハンドバッグ(これは戦前夫からボーナスと一ケ月の給料全部をはたいて贈られたものであった)や、純毛毛糸の登勢が手で編んだ大型ショール等を売って貰って、カンフル注射液を買って来て貰った。(一箱45円。注射液は闇ですごく高償だった。)
衰弱しきった留里は、脈が結滞してカンフル注射を三十分おき位に打たねばならなかった。脈の打ち方も乱れ勝であった。登勢はもう夢中で神に祈っていた。
その夜の事であった。留里が急に咳込んだ。〃あっ〃と思ったのと脈の結滞がひどくなったのが同時だった。
留里の顔はチアノーゼをおこして唇の色はふなめ色であった。登勢は慌ててカンフルのアンプルを歯で噛んだ。注射器を持つ手が震えて注射針がアンプルのガラスに当ってガチガチと鳴った。無我夢中で注射を打ち終えたが、登勢は胸の鼓動がなかなか治まらないで、じっと留里の表情を見つめていた。痛いカンフルの注射を打たれても留里は泣き声もあげず……。意識があるのかないのか?
そのうちに留里の顔からチァノーゼはとれたが、高熱にぐったりとした留里は、時々おびえた様に手足をビクツとさせながら眠りにおちた。
登勢は眠れなかった。眠っている間に若しや?と云う心配が先に立って、まんじりともせず朝を迎えた。
登勢の周囲ででも赤ん坊が次々と死んでいった。
登勢達の後側の元山中副官夫人の処でも、横の上敷領夫人の処でも、柳沢夫人の処でも、夜になるとお経を唱え、お燈明をあげていた。秋乙では長男の坊やを、南浦では次男の赤ん坊を亡くした柳沢夫人は、留里を見ると死んだ坊やを思い出すので、登勢達と少し離れて場所をとっていた。柳沢夫人の悲しみがよく判るだけに登勢も辛らかった。
登勢も愈々留里が死ぬ番ではないのかしら?と考えると恐怖に身のちじむ思いだった〃神様どんなにしてでも子供の命だけは救けて下さい。内地に帰った途端に私の命を代りにお召し下さっても構いませんから、子供をお救い下さい〃。その夜も登勢は一心に祈りながら、30分ー40分置に、カンフルの注射を打っていた。
突然!。登勢達16班の反対側で異様な叫び声がした。それは断腸の叫びであった。思わず立ち上った登勢がそこに見たものは、何とも奇妙な光景であった。
四才位の寝ている幼児に向って、三十才位の母親が大声で何事かを叫びながら、女児の着物を引きちぎる様にしてがむしゃらに投げつけている。
周囲の人々が引きとめてなだめているのに、遂々女児を素っ裸にしてしまった。女児の青白くむくんだ肌には発疹のかげもなく、女児の腹部は死魚の腹を思わせる光沢さえおびて、全身を死の影が静かに支配していた。それと対象的に、裸電球に輝らされた母親の顔は、赤らんで苦痛に歪んでいた。
そのうち、母親はくず折れる様に座して大声をあげて笑い泣きを始めた。三人の愛児を四、五日程の間に次々と死なせた哀れな母親は、遂々気がふれてしまったのだ。隣席の人達が素裸にされた女児の死体に着物を着せかけた。
毎朝、夜が明けると登勢は、子供達が眠っているのを見すまして、汚れたおしめや肌着を抱えて洗濯場へ駈けて行った。
倉庫の建物に囲まれて洗濯場があった。その横は干し場で紐が幾条も引っ張ってあった。少し離れて筵を吊り下げて入口としただけの便所があった。その便所の向う側は石垣をつんで少し高くして簡単な事務所風の建物が建っていた。便所の横は有刺鉄線の垣がめぐらされて、事務所風の建物に近いところに小さな入口があり、そこには若いソ連兵の歩哨が何時も立っていた。
登勢は、子供の事が洗濯をしている間も心配で、愛児の命を悪魔がねらっている様な錯覚におそわれて、駈け足で倉庫へ帰るのだった。倉庫の入口は扉を開けて代りに筵が吊り下げられ、自由に出入出来る様になっていた。筵は倉庫の保温にもなり、開閉の度に大きな音のする重たい扉と違って便利であった。一歩倉庫へ足を入れるとすぐ秀坊の泣声が登勢の耳に感じられ、彼女は飛ぶように筵の席に戻るのであった。
しかし愛児を亡くした夫人達は倉庫へ帰るのも足が重かった。16班では多くの家族達が愛児を亡くして悲嘆にくれていた。山中元副官夫人は乳飲児の長男を、遂々死亡させてしまった悲しみが胸に溢れ、筵の席にうずくまっていた。夫人のすぐ前横に寝かされて泣いている、登勢の次男(秀坊)の泣き声が身に泌みて、その度に乳房がキュンとなって、乳首から涙の様に母乳が滴り落ちた。「おお。よしよし泣かないで?。」思わず夫人は秀坊を抱き上げた。抱き上げられて赤ん坊は泣くのを止めた。そして右に左に首を廻して乳を探した。登勢が倉庫の筵の席へ戻ると秀坊が居ない。「あれ?。」と驚いたトタン・
「奥さん。余りに泣いて可愛想でー。」
山中夫人が秀坊を抱いたま、声をかけた。登勢が
「すみません。小さいのに大きな声で泣いて-。」
と詑びると、
「いいえ、お腹が空いているのと違いますか?。私のお乳あげてもよろしいか?.。」
山中夫人はひかえ目に云った。登勢は余りお乳が出ない体質で秀坊は小さかった。山中夫人の言葉は登勢にとって渡りに船であった。登勢は嬉しかった。
「有難う御座居ます。どうぞお願いします。」
と登勢は深々と頭を下げた。上敷領夫人が横から、
「私の処も坊やを死なせてしまって、子供を死なせた母親の、心はどんなに切ないものか!死なさない様に奥さん頑張って頂戴!。構わなかったら私のお乳も秀坊に飲んで貰って!。」身を揉様にして云う上敷領夫人の眼から大粒の泪がはらはらとこぼれた。乳人の様に秀坊に乳を与えて呉れる人が出来て登勢は嬉しかった。そして有難かった。
〃留里に私のお乳を飲ましてやれる〃。登勢は二人の夫人に赤ん坊をたのんで留里に乳房を含ませた。〃留里はもう駄目かも知れない。出来るだけお乳を飲ませてやりたい〃。それは彼女の切ないまでの母心であった。横では発疹と熱で赤らんだ顔の敏夫が静かに眠っている。通りがかりの樗木が声をかけた。「トシちゃんおとなしく寝ていますね。ルリちゃんはどうですか?.。何とか快くなって貰わないと16班の4才以下の子供は全滅になります。奥さん。頑張って下さい。」
「はい。有難うございます。」
登勢達の筵は通路の傍なので、皆が登勢の不眠不休の看護を励まし力づけて通って行った。
「奥さん。此の間の話の薬、持って来ました。留里ちゃんに飲まされますか?。」街の病院の医務室関係に出入している薬剤師の一幡氏であった。
「有難うございます。」
戦前肺炎の特効薬とされていたバイエル社のトリヤノン末である。登勢は神の救いだと思った。一幡氏は温厚誠実な人柄で皆から信望があった。一幡氏の頭から後光が射している様な思いで、登勢は薬をおし頂いて早速留里にのませた。特効薬と云われるだけあって、薬は偉大な効力を発揮して、熱は三十八度以下に下り、夕方には三十六度八分に下った。〃どうにかこれで留里の病気は峠を越したのであろうか?.でも油断は出来ない。〃と登勢は思った。登勢の指先に感じられる脈博の弱々しい不整脈〃栄養失調の上に高熱が続き何も咽喉を越さなかったので、衰弱がひどかった。
〃うすくなった血液は心臓を持ちこたえられるだろうか?.
〃翌朝、登勢は前田医師に診察をたのんだ。
埠頭の倉庫の住人の中で、〃殆んどの人が完全な健康体ではない。〃と云ってもよい栄養状態である。前田医師は多忙の中から、留里の診察をして首をかしげた。
「大分衰弱がきついですね。五%の葡萄糖注射液が手に入れば打ちましょう。それが無ければもう輸血しか方法が無いですね。注射液を何とか探して見ましょう。一本百円でも良ろしいか?。」
「はい。どうぞお願いします。」
登勢は思った。〃子供の命が助かるなら何も要らない。たとえ多額の借金をして、その為一生を苦労の中に埋もれても構わない。〃
横から上敷領夫人が、
「奥さん。早くお金を持って行った方がいいわよ。それも日本円でね。」と云って教えてくれた。そして、前田医師の処では、何でも手に入る様な意味を臭わせたので、登勢は医師にもいろいろとある。夫岡田軍医の様に仁術に徹した者もあるのにと一寸厭な感じがしたが、ともかく早速お金を持ってたのみに行った。筵に帰って来ると元上等兵の小吉実利が声をかけた。
「奥さん。若し注射液が無かったら、自分は0型だから血をあげます。」
樗木も、
「奥さん!一心配しなくても、私も0型だから輸血の血を上げますよ。」と登勢を慰めた。二人に勇気づけられて登勢は有難かった。
「有難う。すみません。」登勢の声はつまり、眼は有難泪に曇っていた。食糧と云ってもうすいお粥。自分一人の命もどうなるか判らない時に、大切な血液を呉れると云う二人に何とお礼を云えば良いのか判らなかった。
お昼前頃だった。
添寝の様な姿勢で登勢は留里にお乳を飲ませていた。今は母乳だけが留里に与えられる栄養であった。昨日よりも母乳を吸う力が強く加わって来たのが、登勢を力づけた。そこへ、前田医師が五%の葡萄糖注射液をたずさえて現れた。
「少し元気が出て来た様だね。注射液が手に入ったから注射をしましょう。一昨日から二本たのんであったのが今やっと届いたのに、一本はもう要らなくなったので持って来ました。奥さんの処は運が良いですね。」
何処の児か知らないが、注射液が届くのを待たずに、死んで行った児が哀れであった。静かに登勢は目祷をした。
「これで元気が出るでしょう。脈の結滞さえ起らなければ、もうカンフル注射はしなくても大丈夫と思います。」
「どうも有難うございました。」
医師の帰った後、留里は生気を取り戻して来た。前田医師の云ったとおり、脈の打ち方も目に見えて元気になって来た。
「もう大丈夫!!」と思った途端、登勢は急に疲れが出て来た。考えてみるともう十二日間、夜も殆んど眠っていなかった。立とうと、思ってもどうしても足に力が入らない。ヘタヘタと座り込んだ登勢に、
「奥さん、少し休まないと奥さんが倒れたら大変だわ。私が留里ちゃんの番をしてあげますよ。」
上敷領夫人がすぐ横から助け舟を出して来た。遠慮する元気もなく、
「お願いします。」と云うやいなや、登勢はばったり倒れる様に横になるとそのまま眠り込んでしまった。
登勢はそれからどの位の時間眠ったのか?寝ていた時間は長い様であり短い様でもあった。おそらく刃で刺し殺されても起きない程正体もなく睡りこけていた。
敏夫の「おしっこ」と云う声に眼をさました登勢は、バツと驚いて飛び起きて留里を見た。留里も秀坊も静かに寝ている。
敏夫の額に手を当てると、熱は殆んど下っていた。登勢の長い間の緊張がほぐれて、それは歓喜に変って行った。
「あら!。奥さんもう起きたの?。もっと寝ていたらいいのに。」
「はあ、有難う。お蔭でよく眠りました。」
登勢の若い体は僅かの睡眠で、もうすっかり活力を取り戻していた。
太毛糸の大人のシャツの袖口をまくり上げ、ブクブクに着膨れた敏夫を、御不浄へ連れて行きながら登勢は心の中で祈っていた。
〃神様!。有難うございます。お蔭で子供は助かりました。不信仰な私や三人の子供達の為に御恵みを頂いて有難う感謝致します。
きっと内地で私達の事を祈って下さっているクリスチャンの姑(はは)の願いをお聞き下さったのだと思います。有難うございます。
生前二人の孫を可愛がって下さった福崎のお祖父ちゃん有難う御座居ます。お祖母ちゃん有難う御座居ます。亡き二人のお祖父ちゃん孫をお守り下さって有難う御座居ました。神様有難う御座居ました。神様有難く感謝致します。〃
何度も何度も心中で有難う感謝致しますを繰返し、お世話になった16班の人々の援助と励ましに対しても一人一人にお礼を云いたいと思った。登勢は倉庫の人々全員にお礼を云って廻りたい程嬉しく有難かった。
しかし倉庫へ一歩足を踏み入れた途端!。愛児を亡くした人々の悲しみで、暗く淀んだ空気が肌にひしひしと感じられて、彼女は悲しくなった。悲しみは彼女を現実の問題に直面させた。〃
生れて半年は母体の免疫を受けているとは云え、抵抗力のない赤ん坊が殆んど死んで行ったのだ。まだ秀坊は麻疹に罹っていない。こんな衛生状態の中で、免疫があるからと安心して居られるだろうか?。そうだ!。この際に敏夫の免疫のある血液を、秀坊に注射しよう。敏夫は麻疹に罹って発疹が出てから一週間にもならない。敏夫の血液なら免疫性が強く、僅か5ccで充分の筈だ。
「敏ちやん。秀坊に血をやってくれない?。そしたら秀坊は病気しないから。」
「うん。いいよ。」利き分けのよい長男の返事に、敏夫に済まないとは思ったが、早速血液注射を打つ事にした。
血液の凝固を防ぐグエン酸ナトリウムが無いので手早くしないと駄目なのだ。16班で正看護婦の資格を持っている産婆人に云うと快く引き受けて登勢の席へ出向いてくれた。
「敏ちゃん。じっとしているのよ。」
「大丈夫!!。」
敏夫の静脈から真紅の血が注射器に吸われた。秀坊の臀筋に注射針が立てられた。秀坊は瞬間泣き声を上げた。血液が流れる様に動いた。と思ったのも束の間、動きが止まった。
「あっ!。」難波夫人と登勢が同時に叫んだ。
良い具合入っていた血液が詰ったのか、動きが止まったと同時に「パチン」と注射器は破裂した。
3cc以上は入ったが、残りの血液はこぼれてしまった。
〃少しでも良いのだ。小さい体には3ccで充分だ.〃と登勢は自分で自分に云い利かせていた。敏夫が、
「秀坊は泣くから駄目やねえ。注射器がこわれてしまった。僕は泣かなかったよ。」と云ったので、
「坊やはお兄ちゃんやもの強いねえ。」と難波夫人は敏夫の頭を撫でながら微笑した。
麻疹の流行は随分と猛威を振い、その上麻疹から肺炎を起した為、倉庫の住人三千余りりの内の約八分の一にあたる四百人近い乳幼児が死んで行った。
最初は石炭箱に死体を入れて埋葬していたのに、石炭箱も手に入らなくなり、墓地も地元民に荒らされて衣服は亡くなり、その上、野犬が出て食い荒すと云う悲惨さであった。登勢が夢中で子供の看護に明け暮れている間に月も代わり、気温も暖かくしのぎよくなっていた。もう突堤の桜も咲いている筈だがと桜花を一目見たいと倉庫を出て空地へ行ったが、時既に遅く、桜花はもうすっかり散っていた。
満開の時でも色あせて見えたと云う桜は、もう葉桜と云うにもお粗末な程、佗しい落花の果であった。登勢にはそのみすぼらしい桜木は、次々と死んで行った幼い子供達への哀悼の姿勢だと思われた。皆が待ち恋がれた春は、吹雪の吹き荒れる様な倉庫をさけて通り過ぎて行く様であった。