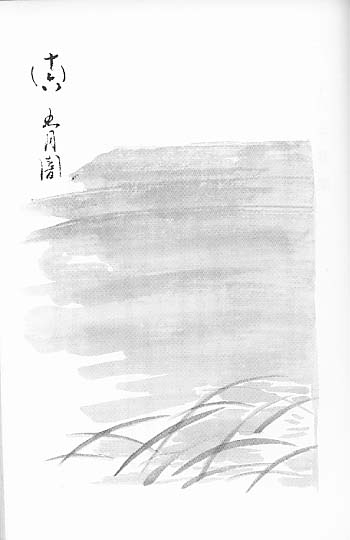
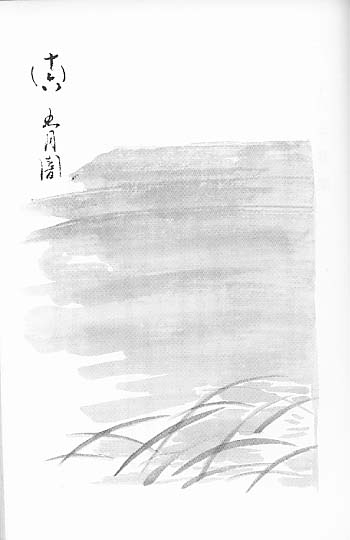
十六 五月闇
昔の駐在所の様な建物にぶらさがった看板に、海洲と云う字が書かれているのが、目についた。
登勢は、〃この辺は海洲だな〃と思った。
そこから二キロメートル程歩いた頃、橋元世話人は、誰かを探しに行った。
南を向いて歩いた様にもあるし、東へ歩いた様でもあるし、登勢達には何処とも判らなかったが、愈々三十八度線に近づいたらしく、越境の為の道案内人に、連絡に行ったらしかった。皆、そのまま、休憩する事になって、道端に腰を下ろした。
愈々、今宵は三十八度線を越えねばならない。
体の震える様な緊張感で、皆は、日の入るのを待った。前の人を見失わない様に、間を空けない様に、声をたてない様に、子供の泣声を出ささぬ様に、最短距離は、河と山なので、頑張って越える様に、と数ケ条の注意があった。
宵闇の静かに迫る頃〃。
橋元省三世話人は、朝鮮語の通訳と、皆の預かり金と案内人を連れて、先頭に立った。
落伍者を出さない為、綱が引っ張られた。けれど綱は、皆が引張ると重くて足が進まない。却って皆が、歩きにくいので、前方から、「綱をはなせ。」と伝言が、さややく様に伝わって来た。
古角芳男は、16班の先頭に立って、大山元部隊長夫人の、衣類や貴重品を入れた大きなリュックの上から、留里をおんぶ紐で結いつけて歩いていた。そのすぐ後に、敏夫、秀坊を背にした登勢、上敷領夫人(夫人は敏子をおんぶしていた。)。
そして、16班の最後は、柳沢夫人、樗木16班長であった。一人の落伍者も出さない様に、落伍者は帰国の希望も、生命の保証もないのだから。
どんな事があっても、子供を離してはならない。登勢は思った。
〃若し秀坊が泣声を出して逃げ遅れる様な時は?。敏夫と留里は?〃
一人子供を見失う事は、四人の親子が死ぬ事であった。
山道を登ったり、下ったり、先へ行く者が止まると、後の音程、長い時間留る事になった。
登り坂の続いた後、暫く下った。月は無く、お誂え向の闇夜であった。
小川で蛙が鳴いて、初夏の訪れを思わせたが、今はそれどころでは無く、前を行く古角に負われた留里の背をじっと見つめながら、敏夫をかばいつ、歩いた。
声を出す者もなく、幼児も親の気持がわかるのか、泣声をあげる児も居ない。敏夫の手をひき、小川を跳びこえた。時々止まっては進み、進んでは止まる。
「クトー(ソ.(誰だ)」「チオ?(どうしたのか?)」行く手に、突然現われた白い服の三人の人影!!。
「出た!!。」「ロスキーだ!!。」
誰もが夢中で後戻りをした。そして逃げた。
散りじりに隊伍が乱れた。何一つ定かに判らぬ暗闇の中で、点呼を取る事になった。橋元世話人以下二百三十人程は、先に行ってしまったらしい。案内人と通訳とお金と一緒に。残された登勢等は途方に暮れた。
後に残された五十人程は、今からの対策を相談することになった。
樗木、一幡薬剤師、保給廠の芦田、元木の主立った男達が、小さな声で皆の意見を聞いて廻った。しかし誰にも良い思案のある筈もなく綾目も分らぬ五月闇が皆を包んだ。
登勢は、これからの方針が、定まる迄と思って、荷物を置いて、秀坊を背から下した。 秀坊を抱いて、ふと見ると、五月闇の中で、荷物が静かに動いて行くではないか?。 さっと手を延ばして、払った手に手ごたえがあった。荷物を引き寄せて、登勢は、その上に腰を下した。引揚者の荷物を闇に紛れて、持って行く地元民があるのだ。深い暗闇の中を、不安な時が流れた。
小柄な男の人影が近づいて来て、柳沢夫人に、
「道を識っていますから、案内をしましょうか?。」と話しかけた。
柳沢夫人が、
「この人が五百円貰えば三十八度線の裏道を案内すると云って居られます。」と云って男の人を、樗木に紹介した。
此の場合、厭も応もなかった。早速、お金が集められて、隊伍を整えなおし、二列で歩き始めた。
先程、現われた白い服の三人は、病人を抱えた家族が、小川を渡る時に遅れて、道を間違って進んでいたので、それを教えたのだと云う事であった。
先頭が行ってしまったので、何も判らぬ登勢達は、道に迷ったのであった。
道案内に現われたのは、鹿児島に行っていて、終戦で内地より帰り、三十八度線で、道案内をしていると云う人であった。 登勢達は、危いところを助かった。
少し進むと、機関銃の音が聞こえ始めて来た。
空砲とは云え、「パリパリパリ。パリパリパリ」と云う音は、気持の良い音では無かった。
先頭から、「皆、人数は揃っていますか?。」という連絡が来た。しんがりを務めている樗木が、
「全員異常なし。」と小声で合図すると、
「これから礼成江を渡ります。ここが一番浅い処です。静かに、早く急いで渡って下さい。」
愈々、最大の難関である。
ソ連国境警備兵の兵舎の燈火が、木の間隠れに見えた。それは恐怖に人を陥れる威嚇の力を持った燈火であった。
折から兵舎に飼っている犬の遠吠えが聞こえ始めた。
登勢は一瞬、足がすくむ思いがしたが、思いきって、流れに入っていった。「敏ちゃん頑張るのよ!!。」と私語いて、敏夫の掌を強く握りしめた。飛石づたいに、浅く見える処へ、敏夫を歩ませて、水をかき分ける様にして、河を進んだ。
水は、登勢の膝下まであった。水の流れに足をとられた敏夫がよろめいた。あわてて、つないだ掌を力一杯上にあげたが、間に合わないで、深みに足を入れてしまった。
腰からずぶ濡れである。
「大丈夫だから気をつけて、ころばぬ様に早く渡るの。」
登勢には、瀬音のざわざわと云う音が、いやに大きく感じられ、胸がどきどきしはじめた。
〃落ちつくのだ!。そして素早く。〃
自分の心を自分で力づけながら、敏夫の手を引いて、水を分ける様に進んだ。
さあ-とサーチライトの光が空を走った。河巾は、もう後僅かになった。心が急いだ。兵舎の燈火も犬の遠吠も、益々近づいて感じられたが、もう恐ろしくはなかった。
敏夫の足も登勢と一緒に、対岸の土を踏んだ。
次は山道だった。もうがむしゃらに黙々と歩いた。いや、よじ登ったと云うべきだ。
胸苦しい程急な坂道を、残されまいと必死になって歩いた。
犬の鳴声も、もう追って来ない。
あと、一息と云う所は、急な傾斜であった。
紙一枚の重さでも、身軽くなりたい一心で、貯金通帖迄も、最後になって捨てた人もあったのだ。
頂上へ昇りきると、上は割合平になっていた。
案内人は、全員が来るのを待っていた。
全員が揃ったので、樗木に云った。
「皆揃いましたか?。私早く河を渡らないと夜が明けたら、ロシヤ兵につかまります。
帰り急ぎます。皆さん、もう大丈夫です。ここから真直ぐに道を下りて行きなさい。アメリカ兵道を教えてくれます。ここで一休みして寝なさい。」
樗木は、礼を云って賃金を支払った。
「元気で行きなさい。もう四時を過ぎています。私、急ぎます。」案内人は、身軽く駈け去って行った。
誰かが、
「これで、やっと、四(世)時二十分(に)世に出たぞ!!」
と、しゃれを云った。
皆は緊張がとれると、心身共に疲れはてて、言葉も無く、倒れた様に転んでいた。
登勢は、礼を云って、古角から留里を受取ると、小さな木の根元で寝させる事にした。 敏夫の濡れた衣服を着変えさせた。敏夫が、
「もう、ロスキーは追って来ない?」と心配顔で聞くので、
「もう大丈夫よ。」と云うと、返事を聞くやいなや、敏夫は、そのまま眠りこけてしまった。子供の稚心にも、一大難関を突破した安堵に、それは終戦以来と云っても過言ではなく、心からの安らかな眠りだったであろう。
その中に、東の空が白み初めて来た。
それは、何とも気持の良い夜明けてあった。
晩春ではあったが、清少納言の〃枕草子〃の巻頭の一節。
(春は曙、やうやう白くなりゆく山際、少しあかりて紫だちたる雲の、細く棚引きたる。)が、登勢の頭に浮んだ。
登勢の心にも紫の瑞雲が棚引いて、蘇生した様な喜びが湧き上って来た。
丹前一枚を掛けぶとんに、山土の褥(しとね)で熟睡する三人の児の横で、登勢も何時しか睡りに落ちていった。
樗木は、16班の班長として、責任を果したと云う安堵よりも、全員、無事に38度線を越えた喜びで一杯であった。
疲れている筈なのに、神経は冴えて睡れぬままに、白み初めた空の、美しい朝雲を眺めていた。
やがて、真赤な太陽が、御来光と云う言葉そのままに、輝きながら姿を現わした。
宇宙の神秘な祝福であった。
二、三時間眠った全員が起きるのを待って、全員揃って山を下る事になった。
地理は判らなくとも、気分的に余裕が出来て来た。
暫く、山を下って、少し道中の広い処へ出た。
前方で、登勢の名を呼んでいる。登勢が出て行くと、そこは遮断機が下りて、丸で汽車の踏み切りの様になっていた。
米兵が、二人と、韓国人の少年が一人居て、検問する所であった。登勢は、とんだ事になったと思った。
一幡薬剤師が先に来て居て、
「刀とお金を出すらしいです。」と云った。米兵は、登勢の顔を見ると、いきなり問いかけて来た。「ホエア、デジュカムフローム?(何処から来たのか?)」
「平壌。(私達の先頭は、先に行きましたが、私達は一緒の団体です)ザトップオブマイグループ、ゴーンァウェー、バットウィァーツゲザーグループ。」「イフユーハヴァナイフ、オアサムシング、ハンドイットツウミー。(刃物を持っていたら出しなさい。」
「ウイドントハヴェニイナイフ、アットオール。(刃は持っていません。何も有りません。)」
横から、チヨコマン(少年)が、
「刀を出しなさい。」と口添えをして来た。
〃この少年は日本語がよく分る〃と登勢は気が楽になった。
小さな果物ナイフを一幡氏が差し出した。
少年が、再び、「刀は無いですか?」と云った。登勢が、「ジスナイフ、オンリーワン。(このナイフ、ただ一つです)。」と答えると、
米兵が、「イフユーハヴェニイマニイ、ハンドィツト、トウミイ。ギブミーオール(お金があったら出しなさい。)ギブ…ーオールザラツジャン、・・リタリー。ノートユーハヴ(ロシアの軍票は全部出しなさい。)」
登勢は、お金を全部出してしまっても大丈夫なのかしら?と不安に思ったので、一幡氏に目顔で合図して云った。
「ウィアベリーブーア、ノーマネー。(私達は大変貧乏でお金は有りません)。」
「アイルギウニーレシート。イフユハンドミー、エニイマニイ。エールビーギヴン、ジャパニーズバンクノート、イン、イクスチェンジ、フォーマイレシート、ウェンユーリターンツウジャパン。」
側で少年が、
「お金の受取りを渡しますから、後で貰って下さい。日本でお金と代ります。」と云った。
「トニー。お金。」と云って、ロシヤの軍票を見せたので、一幡氏は、その由を皆に伝えた。少年は、すばやく、皆が出した軍票や、日本紙幣を数えると、米兵に手渡した。
米兵はゆっくりしていた。
軍票は僅かであったが、軍票を持っている人は、全部出した。
日本円は、人によって出す人と出さぬ人が出来た。
お金のうち、日本円は殆んどの人が肌着に縫い込んでいたので、(ソ連兵やら現地人から取られるのを予防する意味で)一層手間取った。
米兵が、ゆっくりと紙幣を数えて、証明を書き、
「オッケイ。レッツゴー。」となったのは、それでも二時間近くたった頃だった。
米兵と少年に道を教わって、路地の様な処を通り、二里程(一里は四粁程)歩いて、青丹の駅に着いたのは、五月晴の空から照りつける太陽熱で、ホームが熱を反射しているお昼前であった。
ホームは列車を待つ人で一杯であった。屋根のないコンクリートのホームは、溢れる程の人と、照りつける五月の光に熱気をはらんだ様だった。
皆コンクリートの上に、しゃがんだり、腰を下して、乗車の順番を待って居た。登勢達が、ホームヘ入って行くと、離れた処から声がした。
「あー。来た来た!。」
「よかった!。」その声の主は橋元世話人達であった。
橋元省三世話人の姿を見とめるや、保給廠の芦田は、人々を押しのける様にして進んで行った。そして、
「来た。来た。とは何だ。この野郎!。」と云いざま、橋元世話人(引揚団長)の胸倉をむんずとつかんで、鉄拳を浴びせた。
「自分等家族だけ良ければいのか?。道案内人と、通訳を連れ、全員のお金を持って自分等だけ先に行った。その責任を取れ!。」「まあまて、待ってくれ!。」
登勢達は驚いて、揉み合う二人を呆然と眺めていた。
誰かが仲裁に入った。芦田も橋元を殴った事で幾分怒りが治まったか。手をはなした。「これで一寸胸がすいたぞ〃一。」
誰かが大きな声を出した。
それは、闇夜の38度線で、置き去りにされた一行の、偽わらざる心境だったかも知れない。とんだハプニングであったが、
〃内地へ還れる〃〃その思いが、皆のわだかまりを解いた。
皆、以前の融和した一団となって、汽車の順番を待った。
京城の駅で、頭髪も真白になる程DDTを一杯かけられ、京城市内の本願寺に着いたのは、その日の夕方であった。